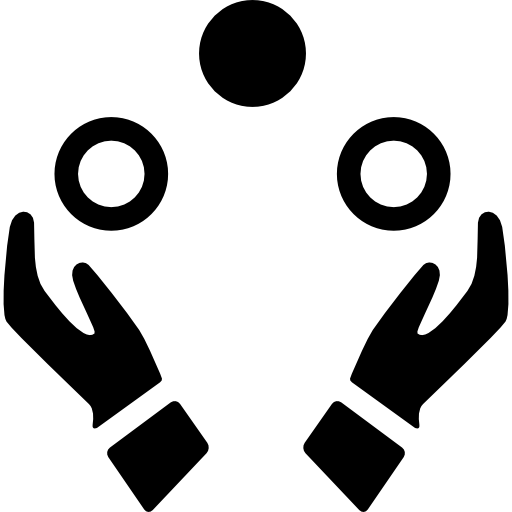どうも、ゴ~チョです。
今回の記事は『ジャグ作』9本目です。
もうお気づきかとは思いますが、このブログでの紹介順と、作品の新旧の順は必ずしも対応しませんのであしからず。あくまで僕の目に留まった順です。
袁藤沖人『ジャグリ』 全2巻

- 作者: 袁藤沖人
- 出版社/メーカー: KADOKAWA/アスキー・メディアワークス
- 発売日: 2010/04/27
- メディア: コミック
- 購入: 2人 クリック: 43回
- この商品を含むブログ (16件) を見る
ジャグリ=大道芸
「ジャグリ」
ジャグラーたちにとっては、すごくざわざわするタイトルですね。
英題の綴りは「juggle」でまさしくそのものですし。
舞台は中世のイスラム文化圏をモデルにした世界。
「砂漠の国」の第三王子のアムシャスは、王子であると同時に町なかのサーカス団「アラテュルカ・アラギュン」の団長も務めています。ここでいうジャグリとは大道芸全般を指すようです(なんだジャグリングじゃないのか...)。アムシャスの披露するジャグリは今日も拍手喝采。しかし客席のなかに笑わない女性が一人。実はその女性、父王が招いたロプ・ノールの民の姫巫女でした。ロプ・ノールの姫巫女は、笑えばその地に太陽を、涙すれば雨をもたらすとされ、普段から感情を封じています。父王はアムシャス含む3人の息子に「姫巫女に涙を流させた者を後継者とする」と告げました。しかしアムシャスはサーカスでの姫巫女の表情が気になったのか「俺は笑わせる!」と宣言します(いやいや王子よ)。さて姫巫女は感情を顕わにすることができるのか、後継者に決まるのは果たして誰なのか...
といったところが大まかなあらすじです。
「ジャグリ=大道芸」ということであまり物を投げたりはしないのですが、現代日本のジャグラーが「ジャグリング」と認識する動作をしている場面は2巻で登場します。しかもけっこう大事な場面です。
緻密な線で構成された壮大なアラビア世界
表紙を見ても分かるとおり、非常に緻密で細かい絵を描く方です。表紙の密度が本編でもずっと続きます。それをアシスタントに頼らず全部ひとりで描かれたそうで、大変な労力がかかったものと窺えます。市場のシーンなど、その場の活気や熱気もそのまま迫ってくるかのようです。
「これはイラスト用の描き方であって漫画の絵の描き方ではない」とする書評もいくつか見られました。確かに、絵の緻密さゆえに人物が背景に埋もれて物語を追いにくいところはあります。作者は元々はゲームのグラフィッカーだったということもあり、そのときの癖のようなものがあるのかもしれません。それも含め特徴かなと思います。
おっと流石に俺では五個が限界だッ
2巻の中盤あたりでお手玉(アストラガリ)が登場します。よくイラストで見かけるありえないシャワー軌道ではない時点で好感度大です。球を持つ手つきもリアル。何よりアストラガリを披露した人物(彼は大道芸人ではありません)のセリフが絶妙です。
「おっと流石に俺では五個が限界だッ」
「なぁに子供は飲み込みが早い
六つ八つはすぐに覚えるだろう」
...趣味ジャグラーには胸に刺さるものがあると思います。5個まではなんとなく練習していてもできるようになってたりするんですよね。6個8個(なぜ7個を飛ばしたのか)になると挫折する人も多数出てきます。それを尻目にキッズジャグラーが平然と8個投げてるのを目の当たりにしたり...作者は個数と難易度の妙をよくご存じのようです。
広げに広げた世界観のその先は...
大道芸、王位継承争い、姫巫女の力、砂漠の大交易都市、過去の戦争、市民にはびこる大麻、ランプの魔神(出てきます)...魅力的な物語の要素盛りだくさんですが、これだけ盛りに盛って、全2巻。果たして消化しきれているのかどうか、それは読んでみてのお楽しみということで(察し)。よくよく取材されたのだと思います。取材して魅力的に感じたことって全部盛り込みたくなりますよね。
願わくば、30巻くらい費やして、この世界観を余すことなく伝えられるスケールの物語を読んでみたいものです。
ではまた!

- 作者: 袁藤沖人
- 出版社/メーカー: KADOKAWA/アスキー・メディアワークス
- 発売日: 2010/04/27
- メディア: コミック
- 購入: 2人 クリック: 43回
- この商品を含むブログ (16件) を見る